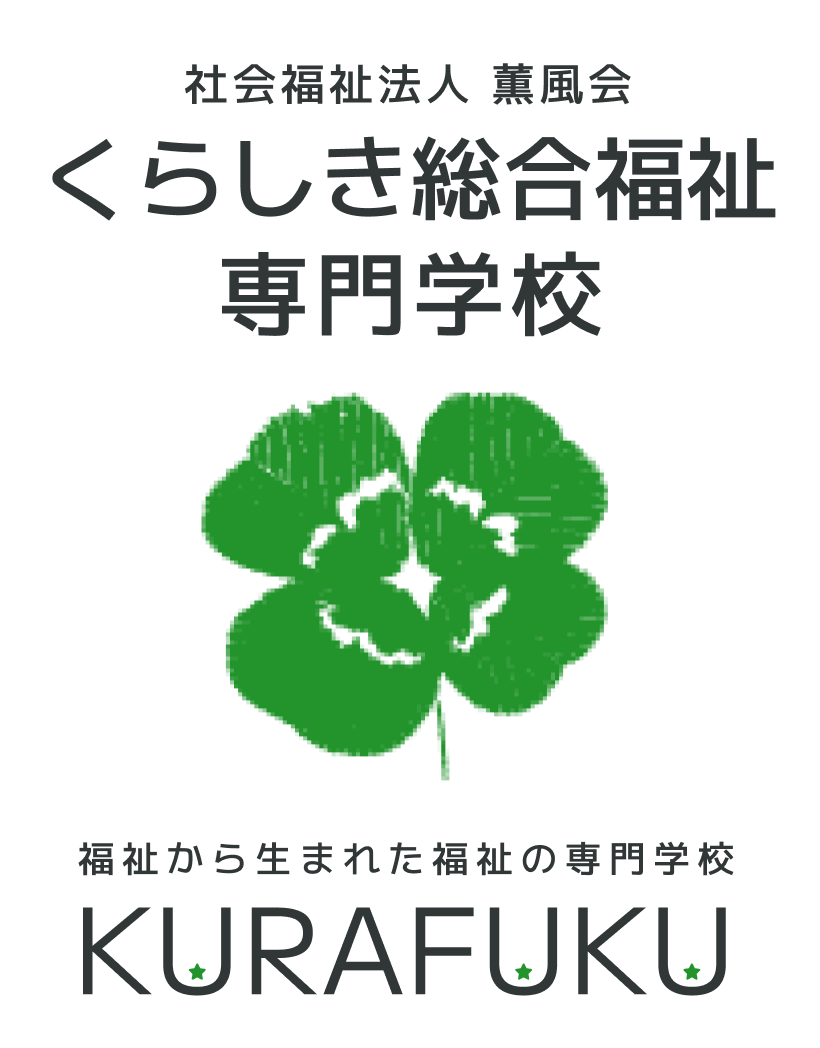“かいごの素朴なギモン”~Q&A
目 次 INDEX
Q1.「介護職の給料は安い」って言われてるけど…
A. ホントは待遇の良い介護のシゴト
介護福祉士は専門学校新卒で大学新卒並み(全国平均) の給料です!
「介護職は給与が安い」とよく言われますが、決してそうではありません。現在、国は2025年問題をはじめとする様々な問題を解決するため介護分野へ多額の予算を投入しています。特に15年ほど前に介護職員処遇改善加算(当初は介護職員処遇改善交付金)が設けられてから介護福祉士の給与は劇的に改善されました。
現在の介護職員処遇改善加算は度重なる改正により一人当たりの月額支援額をⅠ~Ⅳと無支給に分類し、そのランクをもとに手当が支給されています。Ⅰが取得できた施設では月額約5万円相当が「処遇改善手当」として給料にプラスされる仕組みとなっています。
例えば、本校の母体である「社会福祉法人薫風会」では、専門学校新卒者(介護福祉士)の給料は224,000円、これに夜勤のある部署では月額32,000円の手当がプラスされ、標準で月額256,000円支給されています。ボーナスは4.6ヶ月、月に9日間の休みがあり、基本的に残業はありません。
令和6年賃金構造基本統計調査(厚生労働省)では、全産業の学歴別にみた新卒者の残業手当や通勤手当含んだ平均賃金は、専門学校新卒者は222,800円、大学新卒者は248,300円となっていますので、これと比較をすると大学新卒者よりも高くなっているのが現状です。
Q2.介護の職場って…よく辞める!?
A. 資格を持たない方が退職するケースは多いですが、介護福祉士取得者はほとんど辞めません。
一般的に「介護の職場はすぐ辞める」といわれ、退職率の高い職種の一つと思われがちですが、実際の退職率は12.4%(2024年、介護労働安定センター調べ)、同年に厚生労働省が調査した全産業の退職率(雇用動向調査)は14.2%となっていますので、介護職の退職率は全国平均値を下回っています。
しかし、これを資格取得別にみると介護福祉士取得者はほとんど辞めませんが、無資格で介護職に就いた方のうち約7割の方が3年以内に退職しています。つまり、これが「介護は退職率が高い」というイメージにつながっているのです。
無資格の方が退職してしまう理由は
① 介護職の給与にはQ1で述べたように施設間格差があり、ある程度の知識と情報が無いと見極めが難しいことから少ない情報と雰囲気のみで就職してしまったこと。
② 介護職は専門職であることから、技術や知識(介護福祉士)が無いと任せられる仕事には限界があり、それが給与に反映され低めに抑えられていること。
③ 日々の業務には専門用語をはじめとした知識や技術を求められることが多く、また、介護福祉士を取得するためには仕事が終わったあとひとりで勉強しなければならないこと。
などがあげられます。
逆に、養成校で介護福祉士を取得してきた介護職員は、根拠に基づく理論と実践を「講義と実習」でしっかり学んで就職するため、初めからスムースに対応でき、ステップアップの機会もたくさんあります。勤務年数も10年、20年と長く勤める方々もたくさんおられますし、20代で施設の管理者(施設長等)を任せられる人もめずらしくありません。
Q3.介護の仕事はキツいし、ハードだし…大変な仕事だ!
A.いいえ、とても“やりがい”のある仕事です。
逆に一般企業の方がハードかも…
介護の仕事というと、一日中「介護」をしているというイメージが強いですが、実際はそうではありません。
福祉の現場では、ご利用者に生活の豊かさを感じていただくことも大切な仕事です。
例えば、夏祭りや秋祭り、クリスマス会やお花見…といった季節を感じていただく行事をはじめ、将棋やオセロといったテーブルゲーム、書道教室にカラオケ…などの利用者自身の趣味や特技を活かしたアクティビティを日々おこなっています。つまり、状況に応じた「介護の仕事」と、生きがい生活を創造していただく「福祉の仕事」から成り立っているのです。
また、社会福祉法人等が運営する施設の介護職には、残業やノルマはなく、プライベートな時間を十分持てる職種です。一見、華やかそうに見える一般企業での仕事の方が、実は身体的にも精神的にもはるかにキツい仕事なのかも知れません。
Q4.そもそも介護福祉士ってどんな資格?
A. 介護福祉士は生活支援の専門家です。
「介護福祉士(Care Worker)」は「介護」の知識と技術をもった専門家であると同時に、一人ひとりの生活を豊かにする「福祉」の専門家です。つまり「生活支援のため」という視点のもとに、理論と実践の融合を図る福祉系の国家資格です。
一般的に「医療系の資格で、身体介護だけおこなう簡単な資格…」と誤解されますが、決してそうではありません。
介護福祉士は、1987年5月、我が国の福祉分野における初の国家資格として誕生しました。
当時の厚生省は、ドイツの「老人介護士(Altenpfleger/in)」を見本に、他の諸外国で半年程度で取得できる介護系の資格「Care Giver(介護士)」と、ソーシャルワーカー (Social Worker)の理念と技術をあわせ持った日本独自の資格として「介護(care)ができるソーシャルワーカー」という概念を示しました。
当初、資格取得のための要件を「養成課程3年+国家試験の合格」で実施する考えもありましたが、早すぎた時代背景と資格者を増加させる目的で、「養成課程2年以上(国家試験免除)」、もしくは、「介護職の実務経験3年以上+国家試験の合格」として成立させました。
2007年、法改正によりカリキュラムが全面改正されると、目標とする介護福祉士像は「生活支援者として、福祉・介護・医療の知識と技術の基本をおさえ、人間の尊厳と自立・自律をもとに介護過程の展開(ケアプラン)が実践できる介護福祉士」となり、介護が必要な生活全般の支援者としての資格の色彩がより濃くなりました。
同時に、養成課程修了者には国家試験の受験を義務化、実務経験者には半年以上の養成課程(実務者研修)の修了を義務化し、介護福祉士のさらなる質的向上を目指すことになりました。
2011年6月、たん吸引など生活支援にかかる医療行為が医師や看護師などの医療系の資格以外で初めて認められ、今後ますます社会から期待されている福祉系の国家資格となりました。
介護福祉士は他の資格のように完全に完成した資格ではありません。常に「理想的な介護福祉士」を目標に発展し続けています。
10年後…20年後…介護福祉士の重要性はますます高くなっていることは確実です。